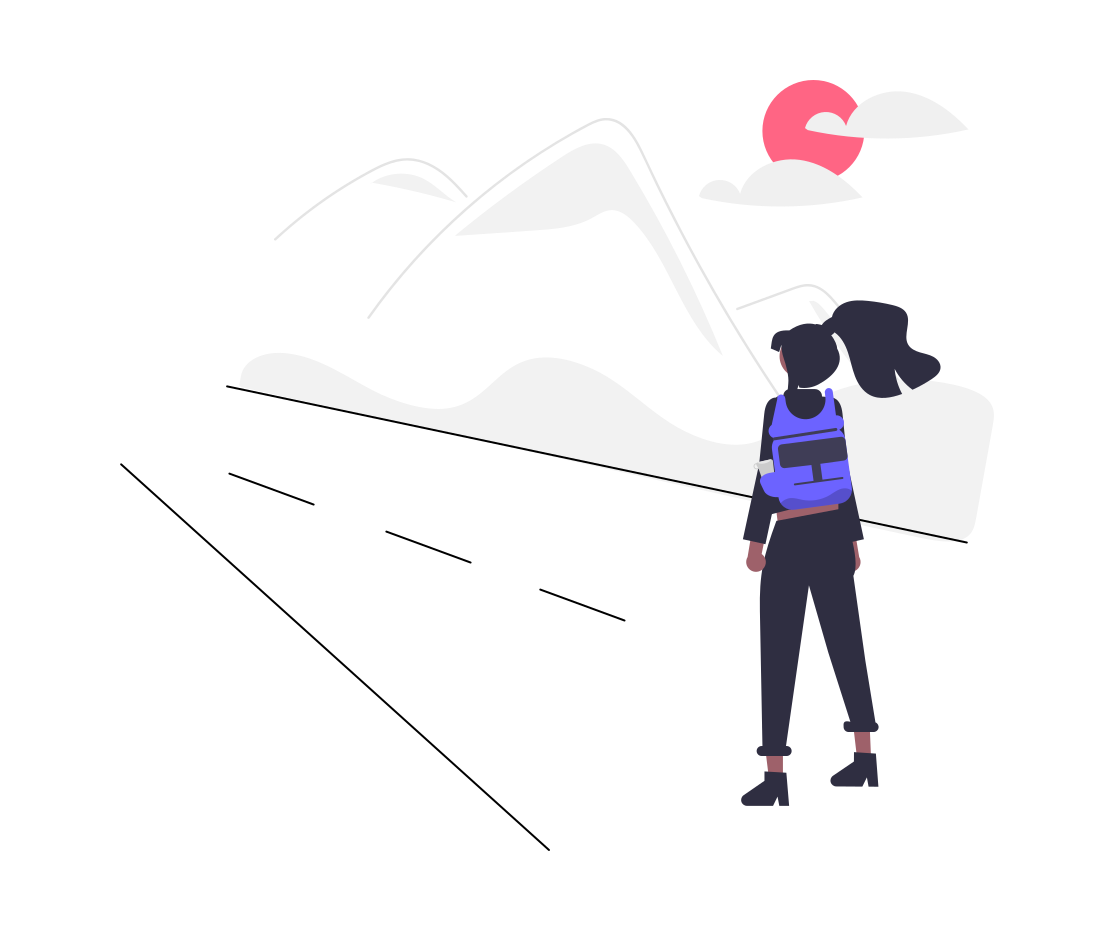2022年に13年勤めた会社を退職し、セミリタイア生活(無職生活ともいうw)に入りました。
以前は、一般的な定年の60歳くらいまでは働くと思っていました。
ところが不思議なもので、そうなるべくしてなるように色々なことが重なり、当初の予定より8年ほど早く、半ば強制的に退職するに至りました。
最近ではFIREとかセミリタイアとか、そういったものがブーム的な感じもありますが、私の場合、それほど楽しい決断ではありませんでした😢。
それでも、現在は少しずつ前向きにリタイア生活を送れるようになってきています。
今回は、私が退職を決断するに至った経緯について書きたいと思います。
これからセミリタイア生活を始める人の参考になれば幸いです。
退職を決心したきっかけ
退職を考え始めたときから実際に退職するまでは約2年ほどあったと思います。
それまでに段階的に色々なことが重なっていきました。
会社の先行き不透明感が強まった
最初のきっかけは会社の先行き不透明感が強まったことからでした。
元々、社員が5人にも満たない零細企業でしたが、細々ながら堅実な経営で創業50年近くにもなっていました。
ところが、ワンマン経営で通してきた社長は80歳近くの高齢になっているにもかかわらず後継もないままで、しかも軽度の認知症も入ってきていました。
それでいて、ずっと究極のトップダウン方式(笑)でこちらに決定権がほぼないため、業務に差し支えることもしばしば出てきてしまいました。
斜陽産業なことも相まって、おのずと業績もガタ落ちでした。
このような状況になると、社長の人望が皆無だったこともあり、私よりも社歴の長いエース級の社員が泥舟から逃げ出すように次々に辞めていき、あれよあれよという間に私が一番の古株になってしまいました。
私は泥舟に最後まで残ってしまったわけです。
その後、社長が少しでも経営方法を改善するなり、私に対する待遇を見直すなどの見込みがないか、様子をみてみました。
しかし、結果は予想通りの見事なゼロ回答でした。
社長は、次々と人が辞めていくにもかかわらず、その理由も省みず、ただただ漫然と同じようなやり方を押し通しました。
一方で、辞めた人が持っていた細々とした業務の責任は全て私に押しつけられた上に、評価も給与も全く上がりませんでした。
この状況になってからは早い段階で辞める方向で考えていました。
加えて、社長の認知症が進むか病気で倒れるかすれば、退職金(わずかですが😅)がもらえなくなりそうだったことが、決断の後押しをしました。

今は、こういう後継者のいない高齢経営者の中小企業ってかなり多いんでしょうね。
スキルの頭打ちとモチベーションの低下
会社の状況悪化は退職の一番の要因ではありますが、それと同時に、スキルアップが見込めないという感覚に陥っていたことも要因の1つではあったかもしれません。
50代にもなると、モチベーションが急激に下がる感覚は共感してもらえる人も多いかと思います。
特に私の場合は、上記のような先の見通しが立たない会社で、新しい仕事を開拓するとかスキルを上げるとかいう気持ちには到底なれず、モチベーションが完全になくなっていました。
会社のせいばかりにせず、もっとやりようはあったのかもしれませんが、私にはバイタリティが足りませんでした。
それが能力不足といわれればそれまででしょう。
ルーティーンの仕事に関しては、元来の真面目な性格もあり😅、淡々とこなしていました。
でも、ひたすら現状維持のかたちを繰り返すのみで、全く進歩のない毎日でした。
そして、この状態を続ければ、10年経っても全く何も変わらないだろうと確信していました。
毎日同じことを繰り返して楽に過ごせるならそのまま会社に居ればいいんじゃないの?と思われそうですが、そうは問屋が卸しません。
傾いた会社の一番の古株として、責任を伴う煩雑な仕事など、生産性のない無駄な労力が増えるばかりの毎日でした。
労力と給与はますます見合わなくなり、また年齢を重ねるごとに、同じことをするにも疲労感は大きくなっていました。
毎日絶望感に陥っていました。

「静かな退職」とかいわれていますが、私にはちょっと無理でしたね。
実際のところは、能力のある限られた人にしかできない技だと思います。
お金の見通しがついた
先ほど「スキルの頭打ち」とは書いたものの、やり甲斐とかスキルアップとかは、それほど望んではいませんでした。
この年齢で、しかも現状の仕事の中でそれを望むのは難しいことだとはわかっていましたので、ほぼ諦めていました。
ですので結局のところ、会社員を続ける一番のメリットは毎月定額の収入が入ってくるとことだと思います。
零細企業ではありましたが、50歳を過ぎても正社員で働き続けられていたことだけは恵まれていたと思います。
それでも会社の逼迫した状況に加えモチベーションの低下で、他人からみれば甘えと捉えられても、当事者としては、限界に達していました。
こんな状況の場合、若い時であれば、収入源を維持するためには現状の会社で頑張るか、転職を試みることになると思います。
しかし、私の場合は50歳を過ぎていましたので、そう簡単にはいきません。
そこで、現在の我が家の資産と、今後の支出についてざっくりと計算してみました。
今までは、そういう計算は全くしてこなかったので、意外だったのですが、「何とかなるんじゃない?」という結論に達しました。
節約に徹していくことは大前提ですが、私が無職でも何とかなりそうでした。
それがわかった時点で「もうここで仕事はひと区切りにしていいかな」という気持ちに落ち着きました。
このような決断ができたのは、現時点では夫が働いてくれているという安心材料があることが大きいのも事実です。
ただし、夫の仕事事情を聞いてみても不安定なところもあり全く安泰というわけではありません。

もしも本当に困ったら、その時に考えようと思います。
その際には仕事は選んでいられないでしょうし、それは覚悟しなければと思っています。
健康寿命はそれほど長くないことに気づいた
最終的には、これが退職の総括的な理由になったのかもしれません。
2019年度の厚生労働省の調査では、 女性の健康寿命は約75歳(平均寿命約87歳) 男性の健康寿命は約73歳(平均寿命81歳)と報告されていました。
私の場合、健康寿命を全うするまで残り23年です。
23年前に何をしていたかと考えてみると、結構最近の記憶になるんですよね。これには愕然としてしまいます。
しかも、今後、年を取れば取るほどさらに時間の経過は早く感じるだろうと思います。
一方、もし一般的な定年の65歳まで働いたとすれば、健康寿命まで、10年しか残されていません。これをどう考えるかですね。
好きな仕事をされている方が定年まで全力投球するのは、それはそれで充実していて羨ましくもあります。
でも、私の場合はその希望はすでに断たれているわけです。
そうであれば、残りの人生がどんなものになるにせよ、時間を100%自分でコントロールしたいという気持ちに突き動かされました。
そして、少しでも長く、健康で自由に過ごせる時間が欲しいと思うようになりました。
もし、後で自分の選択に後悔することがあっても、会社や人のせいにすることは避けられると思いました。
現時点では65歳で定年退職する人より、13年前倒しで自由時間を獲得できていることになります。

こうして得た自由時間をどれだけ有意義に過ごせるかが大きな課題であり、楽しみでもありますね。
守りの準備しかできていないまま突入したリタイア生活
以上が、退職を決断するに至った経緯です。
本当はもっと万全の準備をしてリタイア生活に入りたかったのですが、そううまくはいきませんでした。
意図せず見切り発車的な感じになってしまいましたので、あまり余裕のある生活ではありません。
そんな中でも節約・投資=守りの準備は始めていました。詳しくは別ページに書いています。
-

-
セミリタイア生活のために実践している節約12選と投資
2022年に13年勤めた会社を退職し、セミリタイア生活に入りました。詳しい退職理由は下のページをご覧ください。 こちらにも書いたように、退職は計画通りではなく、見切り発車的にセミリタイア生活に突入して ...
続きを見る
今後、想定外のことが色々と出てくる可能性は大です。
そうなればなったで、「なるようになる」の気持ちで柔軟に対応していくしかありません。
でも、せっかく始めたリタイア生活ですから、そう長くない残りの人生、あまり力まず生活自体を楽しんでいくことも忘れないようにしたいです。
今後も、これからセミリタイア生活を始める方の参考になることを書いていく予定ですので、またぜひ覗いてみてください。